|
プレートテクトニクスが支配する惑星地球の表面では、十数枚のプレートに分
かれたリソスフェア(岩石圏)の相対運動が地震を始め様々な現象を引き起こして
います。日本列島に南からフィリピン海プレートが、東から太平洋プレートが沈
み込んでいるのは有名ですが、肝心の日本列島が何プレートに属するかはこれま
で「藪の中」でした。20年前の本を見ると日本列島全体がユーラシアプレート、
すなわち欧州やアジアと一枚板になっています。15年前の文献では日本列島の真
中に境界が引かれて東日本が北米プレートになっているでしょう。もっと最近の
文献なら北米プレートの代わりにオホーツクプレートと書かれているかもしれま
せん。一体なにが本当なのでしょう。
最近数年間の宇宙測地観測によってこの曖昧な状況が打破されたことについて
お話しましょう。西南日本や韓国のGPS(全地球測位システム)点がユーラシアプ
レートに対して東向きに年間1cmほどで動くことから、その地域がユーラシアプ
レートの一部であることが疑われ始めたのが数年前のことです。筆者を含むグル
ープは上記地域に加え、中国や極東ロシアに展開したGPS点の数年にわたる位置
変化を解析し、これらの地域がほぼ一枚の独立したプレートとして振舞っている
ことを明らかにしました(Heki et al., Jour. Geophys. Res., 104, 29147,
1999)。その範囲は従来アムールプレートと仮称されていたものにほぼ重なり、
「幻のプレート」の存在が実証された格好になります。さらにアムールプレート
の存在が明らかになったおかげで東日本を含む「オホーツクプレート」を無理に
仮定する必要がなくなり、元通り北米プレートのままで諸データが矛盾しないこ
とがわかりました。西日本=アムールプレート、東日本=北米プレートという構
図がようやく明らかになったのです。
それらの境界は一本の線ではなく中部から近畿にかけて数百キロの幅を持って
います。そこでは南からフィリピン海プレートが沈み込んでいますが、陸側は東
海地震の震源域とされる静岡県東部などの北米プレート側と四国や近畿などのア
ムールプレート側に分かれており、沈み込み速度や地震再来周期も同じではあり
ません。北海道南西沖地震で注目を浴びた日本海東縁はアムールプレートが北米
プレートに沈み込む境界ですが、我々がその速度を約2cm/年と定量化したことは
この地域での地震の繰り返しの理解に重要です。
海溝で見られる海陸プレートの衝突では前者が後者の下に沈みこんで一件落着
ですが、沈み込めない陸どうしの衝突では事態が複雑になります。東日本(北米
プレート)と西日本(アムールプレート)が約2cm/年の速度で衝突している中部―
近畿地方もそのひとつです。このような場合プレートの運命は(1)横に縮んで上
下に伸びる、(2)小さいかけらになって横に押し出される、の二とおりです。代
表的な衝突境界であるインドとユーラシアの衝突現場では上記(1)でヒマラヤ山
脈とチベット高原が形成され、さらに大規模な横ずれ断層でブロック化した陸塊
が押し出される (2)が同時進行しています。アムールプレートも元をただせば北
上するインドが東に押し出した大地のかけらなのです。
日本に目を転じると、中部地方は山岳地帯を形成しており(1)がある程度働い
ていることは明白ですが、(2)はどうでしょう。アムールプレートからみた国土
地理院の全国GPS連続観測点の速度を図に示します(沈み込みによる地面の変形を
取り除いて見やすくしてあります)。中部から近畿にかけて東西短縮とともに南
北伸張が顕著です。つまりインド=東北日本、ユーラシア=西南日本とすると、
東に押し出されるアムールプレート=南に押し出される紀伊半島、という相似形
が成り立ちます。東西短縮と南北伸張の地殻ひずみは断層の横ずれによって解放
されますが、その典型例が1995年の兵庫県南部地震です。その原因は中部日本に
おける陸どうしの衝突、その原因はアムールプレートの東進、そのまた原因はイ
ンドとユーラシアの衝突に伴う大陸塊の押し出し、さらにその原因をたどるとゴ
ンドワナ大陸の分裂とインドの北上となります。
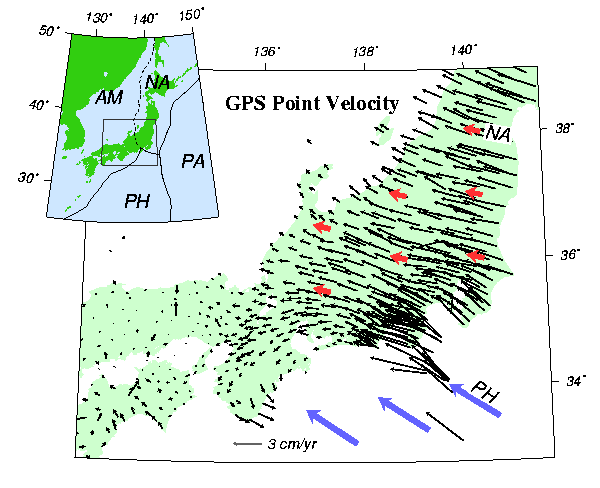
図の説明:左上は日本周辺のプレート(AM:Amurian, PH: Philippine Sea,
NA:North American, PA: Pacific)とその境界。右下はAMからみた国土地理院の
全国GPS連続観測点の速度(黒矢印)と、AMに対するNA、PHの相対速度(太矢印)。
日本列島は中部―近畿を境に東日本(北米プレート)と西日本(アムールプレー
ト)に分けられ、年間2cmの速度で互いに衝突しています。
「国立天文台ニュ−ス No.85より転載」 <日置幸介>
 
|