|
さる 6月13日(土)の10時から16時にかけて、水沢観測センターの施設公開が行わ
れました。水沢地区の施設公開は、小中学校の学校行事と重なることが少ないこの
時期に毎年開いています。例年ですと梅雨入り直前の時期にあたるのですが今年は
梅雨入りが早く、あいにくの小雨模様の天気でした。それでも来場者数は1200人に
なりました。天気が悪くて野外での展示を企画したところは苦労しましたが、かえ
って講演会やポスター展示の方はじっくり見聞いただけたようです。
施設公開の内容ですが、普段から公開している木村記念館のほかに、本館ロビー
では各種研究の紹介、端末室、けやき会館では月探査計画(SELENE)の紹介とビデオ
上映、10mアンテナ関連の施設紹介、講演会などが行われました。
旧本館講堂では、内藤勲夫助教授により「GPS気象学−GPSの天気予報への応用−」
と題した講演会が行われました。精密測量や自動車のナビゲーションに使われてい
るGPSが、どうして水蒸気の観測装置にもなるのか、また天気予報へどのように取
り込まれようとしているのか、最新の研究内容の紹介をいただきました。

講演会の風景
研究紹介では、ポスターを使った各種研究紹介のほかに、地球の自由振動の説明
のために密度の異なるボーリングの球を2個用意して、自由振動の実験が行われま
した。測月学(RISE)グループでは、壁一面の大きな月面の写真や模擬の月の砂を用
意して、月面の雰囲気をかもし出した中での研究紹介となりました。
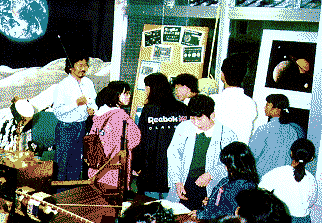
月探査計画(SELENE)の紹介風景
10mアンテナ関連では、国内のVLBI網(Jnet)による成果の紹介や、おりから活動
が活発化しているオリオン星雲の水メーザ源からの電波を実際に受信している状況
を展示しました。また、アンテナ鏡面が集光器になる原理を説明するために、3.3m
アンテナを集音器として使う実験を準備していたのですが、残念ながらこれはうま
くいきませんでした。準備にあたった学生さん、どうもご苦労さまでした。
端末室では、ワークステーションやパソコンを用意して、インターネットの体験
や、天体の写真入り名刺作り、ディジタルカメラを使ったプリクラもどきを用意し
ました。このコーナーは、人気の割に機材やスタッフが不足ぎみで、毎年担当者は
てんてこ舞いしています。
ビデオ上映コーナーでは、科学技術庁長官賞を受賞した国立天文台の紹介ビデオ
「ようこそ国立天文台へ」などを上映しました。このビデオは職員でもまだ見てい
なかった者が多く、来場者をはじめ職員にも好評でした。
工作コーナーでは、銀河系の模型作りと、ペットボトルを用いた水ロケット作り
を行いました。工作コーナーは毎年好評で、来年は2段ロケットに挑戦したいとの
声もありました。
野外では、天体望遠鏡を使って太陽の黒点観測などを予定していましたが、天候
不調のため実施できませんでした。代わりに、遠くに置いた月や惑星の写真を望遠
鏡で眺めてもらい、なんとか観測の雰囲気を味わってもらいました。
さて、施設公開はおおむね盛況でしたが、人気のあったコーナーの中には必ずし
も普段の研究内容とは関係ないものもありました(センター長談)。研究紹介で、
分かりやすくて何らかの体験ができるものを用意するとなると準備が大変になるの
ですが、来年は何とか新しい企画を立てたいと思っております。<田村良明>
 
|