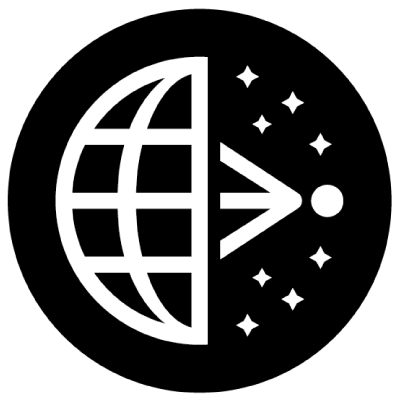天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール周囲の磁場構造を解明
国立天文台水沢VLBI観測所の秋山和徳博士(日本学術振興会海外特別研究員、米国マサチューセッツ工科大学ヘイスタック天文台所属)と本間希樹教授を含む国際研究チームは、米国カリフォルニア州、アリゾナ州、ハワイ州にある電波望遠鏡を結合させて、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールいて座Aスター(Sgr A*)の極近傍領域に付随する磁場の証拠を初めて観測的に捉えました。
詳しい内容は、ウェブリリース「天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール周囲の磁場構造を解明」をご覧ください。